COLUMN
コラム一覧
COLUMN
コラム一覧
category: その他豆知識
最終更新日 : 2025年08月01日
投稿日 : 2025年07月31日

「大切にしていたダイヤモンドのジュエリーを査定に出したら、購入時の数分の一という、想像以上に低い金額を提示されてがっかりした」
そんな経験から、「ダイヤモンドに資産価値はないのでは?」と、疑問を感じていませんか?実際、ダイヤモンドは価値がないといわれることもあるのですが、それはなぜなのでしょうか。
そこでこの記事では、以下の内容を解説しています。
記事の最後には、価値がつきにくいダイヤモンドと価値が高いダイヤモンドの特徴についてもご紹介しています。ダイヤモンドの価値について気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

結論、「ダイヤモンドに価値がない」というのは誤解であり、とくに高品質な天然ダイヤモンドは依然として高い資産価値を持っています。
しかし、購入時の価格と売却時の価格に大きな差が生まれやすいため、「ダイヤモンドは資産にならない」「価値がない」と感じられてしまうのが実情です。この価格差が生まれる背景を理解することが、ダイヤモンドの本当の価値を知るうえで重要になります。
ダイヤモンドの価値が疑問視されるようになった背景には、技術革新による「人工ダイヤモンドの普及」と、金などとは違う「価値基準の複雑さ」という、2つの大きな理由が存在します。
なぜダイヤモンドには価値がないと言われるようになったのか、それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。
「価値がない」と言われるようになった最大の理由は、天然ダイヤモンドと成分は全く同じでありながら、はるかに安価な「人工ダイヤモンド(ラボグロウンダイヤモンド)」が普及したことです。
人工ダイヤモンドは、研究所(ラボ)にて数週間で製造できるため、希少性がありません。そして、見た目では天然品と区別がつかない人工ダイヤモンドが市場に増えたことで、天然ダイヤモンドの希少価値が揺らぎ、中古市場での価格にも下落圧力となっています。
このことが、「ダイヤモンド=高価で希少」という、これまでの常識を覆す一因となりました。
ダイヤモンドは、金のように「1グラム〇〇円」という明確で統一された価格基準が存在せず、一粒一粒の品質によって価値が大きく異なります。
金は、重さと純度が同じであれば、どのインゴットも同じ価値を持ちます。しかし、ダイヤモンドの価値は、4C(カラット・カット・カラー・クラリティ)という複雑な評価基準の組み合わせで決まるため、専門家でなければその価値を判断できません。
この評価の複雑さが、一般消費者にとっての「価値の不透明さ」に繋がっています。
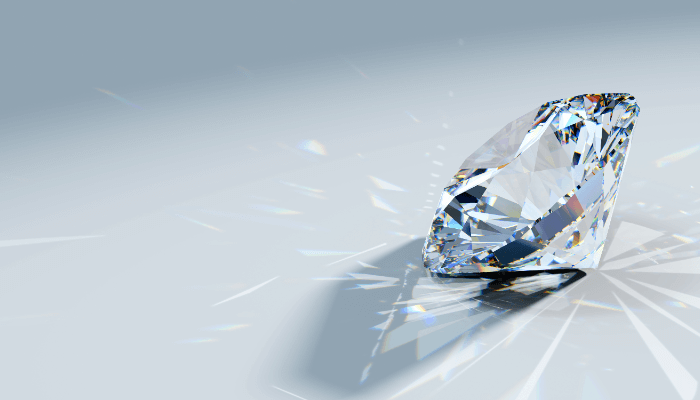
現在のダイヤモンドの価値は、自然が生んだ希少性だけでなく、市場のコントロールと巧みなマーケティング戦略によって、約150年かけて築き上げられてきた、という歴史的背景を持っています。この歴史を知ると、現在のダイヤモンド市場で起きていることの本質が見えてきます。
大まかな年代別に、ダイヤモンドの価値変動に関する歴史的背景を解説します。
19世紀半ばまで、ダイヤモンドはインドやブラジルの一部でしか採れない、極めて希少な宝石でした。その絶対的な産出量の少なさから、ダイヤモンドは王侯貴族やごく一部の大富豪だけが所有できる、富と権力の象徴でした。
この時代、その価値は、まさに本物の「希少性」に裏打ちされていたのです。一般人が手にすることは、ほぼ不可能に近い存在でした。
1870年代に南アフリカで巨大鉱山が発見されると、市場にダイヤが溢れて価格が暴落するのを防ぐため、デビアス社がその供給を独占的に管理し始めました。世界のダイヤモンド原石の流通をコントロールし、市場に出回る量を意図的に制限したのです。
これにより、「ダイヤモンドは希少で高価なもの」という価値観を人工的に創り出し、維持することに成功したのです。現在のダイヤモンドの価格体系の基礎は、この時代に築かれました。
20世紀半ばには、デビアス社が仕掛けた「ダイヤモンドは永遠の輝き」という、歴史上最も成功したマーケティング戦略によって、ダイヤモンドの価値は絶対的なものとなりました。
デビアス社によるマーケティングは、「ダイヤモンド=永遠の愛の象徴」というイメージを人々の心に植え付け、「婚約指輪にはダイヤモンドを贈る」という新しい文化を世界中に定着させました。これにより、ダイヤモンドの需要は爆発的に増え、その価値は不動のものとなったのです。
21世紀に入ると、新たな鉱山の発見でデビアス社の独占が崩れ、さらに技術革新によって、高品質な「ラボグロウンダイヤモンド(人工ダイヤ)」が台頭します。天然と見分けがつかない人工ダイヤが、安価で大量に供給されるようになったことで、「ダイヤモンド=希少」という長年の神話が揺らぎ始めました。
とくに一般的な品質の天然ダイヤは、その価値を大きく見直される時代を迎えています。これが、現代で「ダイヤモンドの価値が暴落した」と言われる、最大の背景です。

ダイヤモンドの価値は、国際的に認められた品質評価基準である「4C」を基本としますが、それ以外にも、いくつかの重要な要素が加味されて、最終的な価格が決まります。
詳しく見ていきましょう。
ダイヤモンドの品質と価値を決定づける最も重要な要素は、以下4つの頭文字をとった「4C」です。
これら4つの要素の評価(グレード)の組み合わせが、そのダイヤモンドの希少性を決定し、価格の基礎となります。現に、世界中のダイヤモンドがこの共通の基準で評価され、取引されているのです。
鑑定書を見れば、そのダイヤモンドの4Cが分かり、客観的な品質を把握できます。
4C以外にも、ダイヤモンドの価値を左右する基準として、「蛍光性」、品質を証明する「鑑定書の信頼性」、そして「ブランドやデザイン性」があります。
蛍光性が強いと価値が大幅に下がる一方、カルティエなどの有名ブランドの製品であれば、そのブランド価値が大きく加算されます。また、GIA(米国宝石学会)発行といった、信頼性の高い鑑定書が付いているかも、その価値を保証するうえで非常に重要です。これら付加価値の有無が、最終的な査定額に大きく影響します。

全てのダイヤモンドが資産として高い価値を持つわけではなく、以下のような特徴を持つダイヤモンドは資産価値が低いといわれています。
これらのジュエリーの購入価格には、素材の価値以上に、デザイン料や加工費、販売店の利益が多く含まれています。売却する際には、その付加価値部分が評価されにくいため、査定額が低くなりやすいです。
それぞれが持つ特徴を解説します。
婚約指輪の脇役や、指輪の腕の部分に敷き詰められている、0.1カラットより小粒な「メレダイヤ」は、資産価値はつくものの、期待できるほどではありません。
メレダイヤは、個別に4Cで評価されることはなく、あくまでジュエリーのデザインを彩る一部として扱われます。そのため、ダイヤモンドとしての一定の価値はあるものの、デザインの一部として評価され扱われることが多いです。
価値の中心は、あくまでセンターの大きな石や、貴金属の地金部分となります。
国際基準である4Cの評価が全体的に低いダイヤモンドも、資産価値はつきにくいです。
たとえば、カラーのグレードが低く、黄色味が目立つダイヤモンドや、クラリティのグレードが低く、肉眼でも内包物や傷が確認できるダイヤモンドは、美しさに欠けるため、中古市場での需要が低くなります。また、カットの評価が低いダイヤモンドは、輝きが鈍いため、宝石としての魅力が損なわれてしまいます。
4Cのグレードは、そのダイヤモンドの美しさと希少性に直結する価値の根幹です。
有名なブランドのものではなく、個性的すぎるデザインのジュエリーも資産価値としては評価されにくい傾向にあります。ノーブランドのジュエリーは、ブランド料という付加価値がないため、その価値は、基本的に地金と石の素材価値のみで判断されます。
さらに、デザインが奇抜すぎると、中古市場で次に買ってくれる人の好みが限定されてしまうため、再販が難しくなり査定額が伸び悩む原因となります。資産価値を考えるなら、誰にでも好まれる普遍的なデザインの方が有利です。
一方で、購入時の価格に近い価値を維持したり、長期的には価値が上昇したりする可能性を秘めた、「資産」として通用するダイヤモンドジュエリーも確かに存在します。以下のような特徴を持つダイヤモンドです。
それぞれ解説します。
カルティエやティファニーといった、国際的に有名で誰が見てもそれと分かるハイブランドの定番商品は、資産価値が非常に下がりにくいです。
これらの製品は、素材の価値だけでなく、ブランドそのものが持つ高い人気と信頼性、そして歴史的な価値が買取価格に大きく上乗せされます。中古市場でも常に高い需要があるため、安定した価値を保ち続けるのです。
1カラット以上の大粒で、かつ、カラー、カット、クラリティの全てのグレードが高い高品質な天然ダイヤモンドは、資産として非常に価値が安定しています。高品質な大粒ダイヤモンドは、産出量が極端に少なく、その希少性そのものに価値があるのです。
ラボグロウンダイヤモンドが普及しても、この「天然で、大粒で、高品質」という領域の希少価値は揺るぎません。まさに、世界共通の「資産」として、その価値を認められているのが、このようなダイヤモンドです。
無色のダイヤモンド以上に、資産として極めて高い価値を持つのが、産出量がごくわずかな、ピンク、ブルー、グリーンといった「ファンシーカラーダイヤモンド」です。とくに、色の鮮やかなピンクダイヤモンドやブルーダイヤモンドは、世界中の富裕層や投資家が収集の対象としており、オークションでは、しばしば史上最高額を更新するほどの価格で取引されます。
これらは、もはや宝飾品の域を超えた、「投資対象の希少資源」として別格の価値を持っています。
この記事では、「ダイヤモンドに価値がない」といわれる理由から、その歴史的背景や資産として価値が下がりにくいダイヤモンドの具体的な条件まで、詳しく解説しました。
多くのダイヤモンドジュエリーは、その購入価格にデザイン料などが含まれるため、資産として見ると価値は下がります。しかし、それは宝飾品としての価値が完全にないという意味ではありません。
お手持ちのジュエリーの思い出を大切にしつつ、その資産価値は冷静に見極める、この2つの視点を持つことが、後悔のない豊かなジュエリーとの付き合い方といえるでしょう。
質屋CLOAKでは、ダイヤモンドの質入れ・買取ともに対応しております。名古屋エリアで「お金が必要になった」「自宅に不要なものがある」などで質屋・買取の利用をご検討されている方は、ぜひ質屋CLOAKをご利用ください。

監修:井上 男(だん)
金や貴金属・ブランド品をはじめ幅広いジャンルを取り扱う「質屋CLOAK」の代表。1977年7月生まれ。
査定歴は25年以上で、年間10,000点ほどの商品を査定。長年培ってきた経験やスキル・最新相場の把握によって、お客様のご希望に寄り添った高額査定を実現中。

名古屋大須の質屋・買取店
PAWNSHOP CLOAK クローク
愛知県名古屋市中区大須2丁目22-4 TEL:052-222-9609
所属組合:名古屋質屋協同組合・愛知県質屋組合連合会・全国質屋組合連合会
質:愛知県公安委員会許可 54116060010A
古物:愛知県公安委員会許可541319806900
Copyright © PAWNSHOP CLOAK クローク All Rights Reserved.